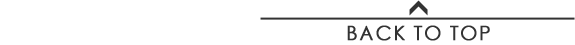監修記事
▪︎2025/7/18 Beauty Park Clinicになべよこ院院長のインタビュー記事が掲載されました。
▪︎2025/1/20 なべよ院院長監修の薄毛の種類についての記事が掲載されました。
▪︎2024/9/20 なべよこ院院長監修の50代におすすめの化粧水についての記事が掲載されました。ランキングについては編集者によるもので院長は監修しておりませんのでご留意ください。
▪︎2024/9/17 なべよこ院院長の一部監修の医療脱毛についての記事が掲載されました。ランキングについては編集者によるもので院長は監修しておりませんのでご留意ください。
▪︎2024/9/13 なべよ院院長監修のナイアシンアミド化粧品についての記事が掲載されました。
▪︎2024/8/5 なべよこ院院長監修のレチノール化粧品についての記事が掲載されました。
▪︎2024/7/17 なべよこ院院長監修の医療脱毛のベストな照射間隔についての記事が掲載されました。
▪︎2024/7/12 なべよこ院院長監修の京都の脱毛クリニック紹介の記事が掲載されました。
▪︎2024/6/28 なべよこ院院長の熱破壊式脱毛についての記事が掲載されました。熱破壊式と蓄熱式の違いについても説明しております。
▪︎2024/5/15 なべよこ院院長監修のの目の下のたるみについての記事が掲載されました。
■2024/1/31 なべよこ院院長監修のおでこのしわに関しての記事が掲載されました。
■2023/12/6 なべよこ院院長監修の肌のくすみ4タイプについての監修記事が掲載されました。
■2023/10/20 なべよこ院院長監修のシミ取りレーザーの種類についてが掲載されました。
■2023/10/20 なべよこ院院長監修の記事東京のシミ取りについてが掲載されました。
■2023/9/29 なべよこ院院長監修の20代AGAについての記事が掲載されました。
■2023/8/25 副院長監修のVIO脱毛についての記事が掲載されました。
■2023/7/1 なべよこ院院長監修のレーザー脱毛についての記事が掲載されました。
■2023/6/16 なべよこ院院長監修のエイジングケア化粧品についての記事が掲載されました。
■2023/5/11 名医のチョイスに眉アートメイクの名医としてなべよこ院院長が紹介されました。
コラム
目次
ステロイドを減らすアトピー性皮膚炎の治療薬デュピクセント®
アトピー性皮膚炎特有の皮膚の中から湧いてくるようなかゆみ、かゆみを我慢するストレス、なかなか他の人に伝わらないつらいことが多いです。今まではステロイドに頼るしかなかったアトピー性皮膚炎ですが、今新しい治療薬が続々と開発されています。
仕事のパフォーマンス、アピアランスやかゆみによる睡眠不足など、日常のQOLを従来の治療とは違うレベルで改善できます。
生物製剤はデュピクセントやアドトラーザ、ミチーガなどの生物製剤があります。年齢や、症状の強さ、副作用などのを総合的に判断して治療に使える薬剤が増えてきました。
デュピクセントはIL-4とIL-13というサイトカインの働きを直接抑えることで皮膚の2型炎症反応を抑制します。アトピー性皮膚炎特有の皮膚の中で起こる炎症反応を抑えることによって、かゆみが改善し皮膚炎を治療していきます。今までの治療でうまくいかなかった、通院が続かなかったなどでお困りの方にお使いいただきたい治療薬です。15歳以上の方が適応となります。
アドトラーザはデュピクセントと相性が悪かった方や症状の強さや年齢の違いにより選択されます。
発売されて数年がたちますが、当初から治療を開始された方の現在の改善ぶりには驚かされます。外用では抑えきれなかった皮膚の中のもやっとした赤味が少しずつ改善されていくのを診療を通じて実感しています。ですが、デュピクセントを打てばすべて解決するという夢の薬ではありません。アトピー性皮膚炎は日常の生活環境や、習慣、その時のお疲れ具合など、様々な要因が絡み合って症状として出てきますので、日々のスキンケアはとても大切です。デュピクセントを打ちながら、抗アレルギー剤や適宜ステロイドの外用剤を併用する方法をとられている方が多い印象です。ですが、デュピクセントを使う前に比べると格段にスキンケアにあてる時間が減っている方が多いと思います。
保険診療のお薬ですが、自己負担額が高額になってしまうため、医療費助成の対象となる場合があります。社会保険の方はお勤め先の医療保険の制度によって自己負担の上限金額が異なります。国民健康保険加入の方は各自治体によりますので健康保険証に書かれている保険者に問い合わせして、金額を把握されてからの受診していただいた方が診療がスムーズです。学生さんなどは学校が補助をしてくれる場合もありますので、各学校の学務課にお問い合わせください。
当院ではデュピクセントの自己注射の指導を行っております。最初の2回当院で自己注射の方法について指導させいただきます。その後は何か月分かを自宅で継続していただきます。自己注射というと痛そう、針を見るのが怖いなどいろいろとハードルはあるのですが、通院のためにお仕事を休んだりというストレスがなくなりますので、はじめ少し勇気をだしてトライしていただければ長く続けられる治療法です。針をみないで打てる補助具などもありますので、いわゆる注射の動作をしなくても打てる方法がございます。わからないこと、不安なことございましたらご相談下さい。
アドトラーザは保険診療の規則により現在は通院注射のみの適応となっております。
アトピー性皮膚炎の方の日常のストレスから解放されてスッキリとしたお顔をされているのを拝見するととても嬉しいです。
じんましん(蕁麻疹)
蕁麻疹(じんましん)は、突然赤みやかゆみをもった発疹ができる病気のことです。蚊に刺されたような発疹や、地図のようにみえる発疹、目や唇が腫れるようなものなど体のいろいろなところにできます。皮膚の中の免疫細胞がバランスをくずすと肥満細胞がヒスタミンとよばれる物質が放出されます。ヒスタミンが血管や神経に作用して皮膚のふくらみやあかみ、痒みを起こします。症状がひどいとのどが腫れてしまうため命にかかわることもあります。
原因として有名なものは食物アレルギー性のものですが、実際に数は少ないです。ほとんどは風邪などのウイルス、過労による免疫バランスの悪化、薬などがきっかけで起こる特発性じんましんです。この他にもコリン性じんましん(痛みのあるじんましん)、物理刺激によるじんましん、血管性浮腫、寒冷じんましんなどなど多岐にわたります。そのため診断には専門の皮膚科医を受診することをおすすめします。慢性化してしまうと治療に数年かかってしまう場合もあります。
治すのであれば何となく薬を飲み続けるのではなく、しっかりと治療をすることです。
以前は抗ヒスタミン剤、抗アレルギー剤、ステロイドの内服などしか治療の選択肢がありませんでしたが、最近では最新の抗アレルギー剤、ロイコトリエン受容体拮抗薬、抗IgE抗体製剤「ゾレア」などがあります。今までの治療でも何となく治らないという状態が続いている方や、飲めば落ち着くけれど何だかいつも体がかゆい、普通の薬をのんでも全く収まらないなどの症状の方は新しい治療法に進むときかもしれません。
また、原因についても様々なパターンがあることがわかってきています。アレルギーについて詳しい医師に相談することが大切です。
当院では東京医科大学皮膚科アレルギー外来と連携しております。実は特殊なアレルギーだったり、特別な治療が必要な場合は、その分野の専門医へ適切にご紹介することができます。
脂漏性皮膚炎のスキンケア
当院では脂漏性皮膚炎の方へのスキンケア指導をおこなっています。脂漏性皮膚炎は乳児期と思春期以降によくできるといわれていますが、日常診察していると幅広く全年齢の方にお越しいただいている感じがします。
主に口、鼻まわりに強く出ますが顔全体、耳、頭皮、脇や股などにできます。時間がたつとべたべたして場所を想像していただくとわかりやすいと思います。
原因は皮脂や化粧品の中に入っているトリグリセリドが皮膚常在の真菌、マラセチア菌に遊離脂肪酸に分解されて刺激物になることでおこる皮膚炎です。肌にぬった化粧品の中のトリグリセリドが時間がたって夕方ごろ遊離脂肪酸になると、なんだか肌がむずむずするという症状を起こします。夕方症状が悪化するとおっしゃる方が多いのです。
当院では脂漏性皮膚炎の原因をしっかりご理解していただいて、常在菌を少しでもおさえる外用剤の継続的な治療と、油分の少ない化粧品を使用していただくよう指導しております。ノンオイルの化粧品としてNOVのAシリーズやアクセーヌのADラインをご紹介しております。基礎化粧品から油分を抑えるということも大切ですが、ファンデーションなどでもリキッドファンデーションなどは油分が多いため注意が必要です。脂漏性皮膚炎になりやすい方はそういったところを気にして化粧品を選んでいただくとよいです。
よく、肌が弱くてどの化粧品をぬっても赤くなるという症状の方がいらっしゃいますが、油分が負担になっていてどの化粧品も合わないという方が多いように思います。化粧品の成分にかぶれているというアレルギーの方もいらっしゃるので皮膚科医の診断をお受けください。
常在菌と油分、どちらも常に皮膚にあるものですし、必要なものでもあります。この2つが主な原因のため通常の湿疹などと比べてすっきりと治って再発がないということがないので、良い状態を維持してうまくお付き合いしていくということが大切です。
菌が影響しているため体の免疫の状態もとても大切です。疲れていたり、寝不足だったり、不足、脂肪酸の多い食事なども影響します。状態がよくなれば外用の回数や間隔をのばすことが可能です。
菌に対して強くなるためには皮膚のバリアー機能もとても重要になりますが、クリームを塗る=保湿と多くの方が考えがちなのですが、「保湿は保水」とご説明しております。水分量がとても大切なのです。化粧水でしっかり保水することが本当の保湿になります。(アトピー性皮膚炎の方など生まれつき皮脂成分が少ない方はしっかりクリームを塗っていいただきたいです。)
脂漏性皮膚炎でお悩みの方はご相談ください。
季節の変わり目の帯状疱疹・帯状疱疹後神経痛
帯状疱疹は水ぼうそうのウイルスが原因でおこるります。水ぼうそうのウイルスは殆どの人が体の中に眠った状態でもっているのですが、過労やストレス、特に季節の変わり目には体の免疫力が低下しやすいため帯状疱疹を発症する方が増えます。癌や免疫不全を患っている方は発症しやすいですが、普通の状態の方でもよくおこる病気です。
皮膚炎の前に痛みが先行することがありますので、皮膚に何もないのに痛みがでてきたなどの症状は注意してください。
帯状疱疹は皮膚と神経を攻撃するため、皮膚の水疱や神経の痛みがでます。放置しておくと水疱が悪化して治ったあとも深い傷跡や色素沈着が残ったりします。特に気を付けなければいけないのは神経を侵す合併症です。
帯状疱疹後神経痛といって、急性期の痛みが慢性の痛みに移行し、皮膚炎が治っても耐え難い痛みや、違和感、不快感が残ってしまいます。後遺症の中で最も頻度が高く、高齢の方ほど痛みが残りやすいため、早期の治療が大切です。
顔に症状がでた場合は目の角膜炎、耳の難聴、めまい、耳鳴り、口の味覚障害などが起こる可能性があり注意が必要です。頻度は少ないですが重症の場合は運動神経のマヒが起こることがあります。顔面神経のマヒ、膀胱の神経のマヒなど日常生活に大きな影響をうけてしまうことがあります。
これらのリスクをなるべく回避するためには、正確な診断と早期の治療ですが早期すぎると診断がつかないことがありますので注意が必要です。
治療の基本は抗ウイルス剤の投与と痛み止めの内服です。
痛みを無理に我慢していると脳が痛みを敏感に感じてしまうようになってしまうため、適切に鎮痛剤を内服することが帯状疱疹後神経痛を残さないようにするためにも大切です。また、神経痛は冷えに弱いため、エアコンや気温などで患部が冷えやすい状態になってしまうと痛みが出やすくなります。
症状に合わせて適切な処方が必要ですので、ご相談ください。
巻き爪・陥入爪について
足の親指の爪の湾曲が強く、爪の端が親指の皮膚を傷つけてしまい痛みがでたり、その傷から感染をおこして腫れあがってしまっている状態です。
多くの場合爪の切り方に誤りがあります。足の親指の爪を切るときにはカーブをつけてはいけません。手の爪切りと足の爪切りを兼用している方が殆どだと思います。足の爪はストレートタイプの爪切りを使用して、爪の端には白い部分が残るようにまっすぐに切るようにしてください。
爪の湾曲が軽度の場合はテーピングやグラスファイバーでの矯正治療(自費診療)が適応となります。また、爪の伸びの遅い方は漢方薬などで末端の血流を改善することも大切です。また爪白癬という水虫菌に侵されている場合もありますので検査をすることもあります。
爪の湾曲が強く皮膚に食い込んで痛みがある場合は陥入爪処置(保険診療)が必要となります。当院では形成外科専門医がおりますので、陥入爪処置は当日行うことができます。患部の指を麻酔してからの処置ですので痛みから解放される方がほとんどです。
巻き爪の原因については、切り方だけではありません。持って生まれた爪の弾力や厚さ、加齢、末端の血流の低下や、日常の歩き方の癖(足の親指の先までを使わない歩き方)、靴の選び方など様々な原因で起こります。
痛みをがまんしていると症状が悪化したり、患部の足をかばって反対の足まで悪化するという悪循環がおきてしまいます。
当院では爪を含めたフットケアも行っておりますので、違和感があるなと思ったらご相談下さい。(外反母趾については整形外科をご紹介させていただきます。)
顔のにきび・胸せなかのにきび
にきび、されどにきびです。思春期だけでなく大人になっても悩まされます。原因は毛穴に住んでいる常在菌が原因のため、原因がとりのぞけません。そのため治療が長くつづきますし、日々の生活も重要になってきます。
菌に対しては免疫力が影響するため、寝不足、疲れ、ストレスなどで免疫力がさがると悪化します。また、常在菌が皮脂を分解してできる酸が炎症を起こしてしまうのでさらに毛穴の入り口が腫れて炎症をおこしやすい状態になります。顔にできる少し大きめの、痛みのあるにきびはアクネ菌という毛穴に住んでいる細菌が原因です。昔は抗生物質ぐらいしか治療の方法がなかったのですが、最近は毛穴のつまりを改善させる治療薬が保険適応となったので治療の選択肢が増えました。通常は毛穴のつまりをとる薬と抗生物質を併用していきます。
同じにきびにみえますが、口まわりやくび、胸、背中にできる細かい、あまり痛みのない小さいにきびはマラセチア菌という皮膚に住んでいる真菌が原因でできます。真菌が原因のマラセチア毛嚢炎という病気の場合は通常のにきび治療をしていても改善していかないことが多いのです。毛穴を詰まらせる原因を改善する薬を外用したり、真菌をおさえる外用剤を使用します。
生理前には皮脂の分泌が過剰になりやすく、皮膚がむくんでいるため炎症反応が強くでやすい時期ですのでにきびが悪化する方が多いのです。生理不順などある方、冷え性などがある方、炎症反応が続いてしまう方は通常治療に漢方薬を併用することで改善します。
男性の場合は皮脂の分泌が多いということも原因ですが、多くの方の場合髭が生えているために物理的に毛穴に刺激を受けやすく炎症を起こしやすいのです。自費診療になりますが、髭のレーザー脱毛も選択肢の一つです。
にきびの治療は保険診療から自費診療まで様々です。
またいらっしゃる方の治療の希望も炎症がおさまればいいや、という方から根本的な治療をご希望の方まで様々です。
当院でにきびでお悩みの方に幅広い治療をご提供させていただいています。
通院の間隔や、予算、治療のゴールがどの程度かによって治療法をご提案させていただいています。
皮膚のお悩みの度合いは人それぞれです。気になることはなんでもご相談ください。
注)現在日本の健康保険制度ではにきびの治療に保険診療と自費診療の混合診療は認められていません。そのため、保険診療の薬を出しながら、自費診療のピーリングをしたりということができません。自費診療を行う場合、にきびの治療に関してのお薬は全て自費診療となります。
足の湿疹(水虫・異汗性湿疹)
足のかゆみ、水疱、ぶつぶつ、湿疹、皮むけ。長時間靴をはいている現代人には身近と言えるほど多い足の湿疹があります。湿疹といっても原因は様々です。見た目がとても似ていて皮膚科の専門医でもみただけでは診断がつかないものがあります。
異汗性湿疹と足白癬(水虫)です。掌蹠膿疱症も足に水疱ができますが、多くは濁った黄味がかった白い水疱です。
手足は体中で一番汗の腺が多いところです。その汗の腺に炎症を起こして管がつまってしまうためとてもかゆい水疱ができてしまうのが異汗性湿疹です。原因はわかっていません。治療は湿疹の薬を外用します。かゆみ止めの内服は掻いて傷をつくってしまうのをとめるために補助的にします。それとよく似たものが足白癬(水虫)です。手にもできます。かゆい水疱ができたり皮がむけたりします。ひらひらとした皮や水疱の部分をとって顕微鏡で白癬菌を確認します。ところがここで市販の水虫のお薬を使用中の場合、白癬菌が確認できないのです。
湿疹の薬と白癬菌の薬は全く反対の作用をします。白癬菌に湿疹の薬を外用すると一時的に良くなるのですが、また悪化してしまうことがあります。外用してみて経過を診るという治療的診断という方法もあるのですが、できれば最初に確定診断ができるほうが良いと思いますので、手足の湿疹でおかかりの際は市販の水虫のお薬は1~2週間は外用をストップしておいていただけると良いと思います。
外用剤は接触皮膚炎(かぶれ)をおこすこともありますので、汗なのか水虫なのかかぶれなのか、という状態になってしまうと治療に難渋してしまうことがあります。
自己判断をせずにまずはご相談ください。
円形脱毛症
自己免疫疾患というのは、自分の体のある部分を自分の免疫機能が敵認識をして攻撃をはじめてしまうという病気です。いろいろなターゲットがあって、いろいろな病気があります。特に多いのが膠原病という病気のグループです。
円形脱毛症と膠原病は直接関係ありませんが、症状の一つとしてでていることもあるので検査をすることがあります。
自分の免疫機能が普段と違う動きをするようなきっかけが発症のきっかけになることが多いです。
風邪や疲れがひどいということも免疫機能が普段と違う動きをするきっかけになりますし、ストレスも免疫低下の原因となります。治療としては過剰な免疫の動きを抑えるステロイドの外用や局所注射が中心となります。
局所注射は1~1か月半に1度の注射となります。保険適応となります。
多発型(全体の25%の範囲)などは局所免疫療法の適応となりますので、該当の方を当院では東京医科大学の脱毛外来をご紹介しております。
眉毛などの脱毛がある場合はステロイド治療もありますが、眉毛部のステロイド局注は強い痛みを伴いますので、当院では眉毛のアートメイクを行っております。
ウイルス性いぼ治療
当院では治療は保険治療の標準である液体窒素療法をおこなっています。液体窒素療法は人工的に冷たいやけどをおこすことでウイルスが住んでいる皮膚を壊して物理的に除去する作用と、やけどによって炎症をおこすことで体の中の白血球をウイルスがいるところへ呼び寄せて免疫的に除去する作用の2つがあります。調べると民間療法から自費診療まで様々な治療が玉石混在していますが、液体窒素療法が最も理にかなった治療法です。施術後は2,3日痛んだり、水膨れになったり水疱に血がたまったりしますが良い反応です。また、ウイルスがいる部分の皮が固くなりすぎてむけていかないといういことがある場合は塗り薬、張り薬や、削る処置をして液体窒素療法がより良く効くようにします。塗り薬や張り薬でイボ自体が治るわけではないので液体窒素療法をつづけてください。
治療には1週間~2週間に1回通院してください。
継続的に治療をすると治癒していきますが、ウイルスのタイプによって治りやすい、治りにくいなどにかなり差があります。ウイルスのタイプは2,3回で治癒するタイプから10回以上処置が必要なタイプまでさまざまです。放置しておくと増殖していぼはゆっくりですが大きくなるため、踏むと痛くなったりなど症状が強くなります。治療は小さいうちにはじめることをおすすめします。タコか魚の目かとおもっていたらイボだったということはよくある事例ですので、自己判断せずにまずは受診してみてください。
お顔のしみ
「お顔のしみ」と言っても実はいくつも種類があります。大きく4つのシミがあります。
①女性のシミ「肝斑」②紫外線のシミ「老人性色素斑」③加齢によるイボ「脂漏性角化症」④ほくろ「色素性母斑」です。ほかにも雀卵斑や炎症後色素沈着、尋常性疣贅などさまざまありますがここでは4つをご紹介します。
女性のシミ肝斑は20歳過ぎたころから両方の頬に点だったり、くすみのように見える薄茶色のシミです。女性ホルモンと紫外線が原因といわれています。妊娠出産を機に強くでることもあって女性であれば殆どの方がお付き合いをしていかなければならないシミです。いわゆるレーザー治療が良く効く方とそうでない方といらっしゃいます。効果があるとされているのはトラネキサム酸という薬です。内服をしたり、外用をしたり、イオン導入したりと様々な治療法がありますが、基本的にはお付き合いしていくというスタンスで美容治療の範囲となります。
紫外線のシミ老人性色素斑は部分的な濃い茶色のいわゆるシミです。加齢と蓄積された紫外線ダメージといわれています。色素レーザーの治療が良く効くシミですので、ポイント照射のしみとりレーザーが適応です。ですが、消しゴムのように消す治療ではありません。色素を持った細胞をレーザーの反応でやくことによって皮膚を再生する治療ですので、照射後かさぶたになってそれがはがれるまで経過2週間ほどはパッチなどを貼って生活することになります。GW前後になると紫外線の量がとても増えますので、日ごろからのUVケアは大切です。
加齢によるイボも同じく紫外線ダメージの蓄積によってできるもので、良性腫瘍に分類されます。しみとおもって受診される方が多いのですが、実はイボということがよくあります。こちらの場合は保険診療の対象となりますので冷凍凝固や焼却術などの治療となります。
ほくろも色の薄い場合はシミと思ってしまいますが、こちらの場合は皮膚の奥のほうに母斑細胞というほくろをつくる細胞が増えていますので保険診療の手術が適応となります。ほくろの分類もいろいろとあって、表面的なものから真皮の下の方まであるタイプとあります。母斑細胞はメラニンをもっていて黒い場合もあれば持っていない場合もありますので色素レーザーでは取り残しがあり再発します。表面を削るという処置も同様に細胞の取り残しがあり再発しますので、麻酔をしてしっかりとほくろを取りきる手術が必要です。
なかなか判断が難しいものですよね。自己判断せずにまずは専門医にご相談ください。
鼻・口まわりの赤みとにきび
現在マスクを長時間つけなければならない状況のために、今まで脂漏性皮膚炎やにきびがあまりできたことがないという方でもそういった症状がでて受診される方が増えている印象です。急激な環境の変化にストレスも加わり皮膚の調子が悪化してしまうこともあります。脂漏性皮膚炎やにきびは皮膚への過剰な油分と免疫が落ちることで原因となる常在菌が増えて症状が悪化します。長時間のマスク着用による蒸れや、擦れることによる刺激も原因です。
そんな時は洗顔をしっかりと行った上で、油分の少ない化粧品を使って水分補給をメインにすることをお勧めしています。大切なのは水分です。当院ではオイルフリーの化粧品もお勧めしております。症状がとても軽い場合は化粧品の使い方を見直すだけで改善することもありますが、基本的には原因となっている常在菌を抑える外用剤と炎症に対しての外用剤が必要です。脂漏性皮膚炎とにきびは同じようなところにできてしまうので判別するのが難しいのですが、通院していただいて外用剤の使い方を覚えていただけると皮膚炎と上手に付き合っていくことができるようになります。にきびについては菌を抑えるだけでは堂々巡りになってしまいますので、菌を抑える薬と毛穴のつまりをとる薬を併用する必要があります(保険診療の場合)。こちらについても上手に薬を使ってお付き合いしていく必要があります。
そして大切なのは免疫が落ちないように日々生活することです。適度な運動、食事、睡眠です。1日1回は汗をかいて呼吸、心拍数を上げるような運動が必要ですし、ついつい食べ過ぎてしまいますが日々の運動量に合わせた食事量が大切です。適度な運動が適度な睡眠に繋がります。何か不安なことがあって寝つきがわるい、寝れないなどの症状がありましたらがまんせずに専門医を受診するようお勧めしています。
手湿疹について
最近手を洗う回数やアルコール消毒の回数が増えているため手にかゆみや湿疹、亀裂のある方が増えています。通常は冬に多いのですが、今年はまだまだ続いています。手の湿疹といってもいろいろなことが原因でなります。アルコールなどの刺激による刺激性皮膚炎、手袋のかぶれによる接触皮膚炎、汗の腺がつまってしまう異汗性湿疹、水虫が原因の手白癬などなどです。検査が必要なものもありますのでご相談ください。
気をつけたいのは爪の根本の皮膚の炎症です。爪の根本には新しい爪をつくる細胞が集まっていることろがあります。そこに炎症が長引くと生えてくる爪が変形してきてしまいます。
基本の治療は皮膚の保湿とステロイド外用で炎症を抑えることですが、保湿が特に大切です。こまめにヘパリン類似物質やワセリンなどの保湿効果のあるものを外用することで皮膚のバリア機能を保ちます。皮膚が乾燥することでバリア機能は下がりますので感染症をおこしたり、かぶれをおこしやすい状態となってしまいます。傷ができることで食中毒の原因菌をふやしてしまったりとあまりよいことがありません。ヘパリン類似物質は傷があるとしみてしまったりかゆみがでてしまうことがありますので使い方も重要です。
ステロイドの外用も大切ですが、日中は手を洗うことなどもあって塗ってもすぐとれてしまったり、食品をさわったりするので塗れなかったりとありますので当院では昔ながらの処置ですがリント布をつかった密封療法をご指導しております。主に夜就寝前に処置をしていただくことで傷の修復と炎症を抑える薬がしっかりと浸透させて、保湿ができます。外用のタイミングは生活スタイルやお仕事の内容によって塗れる時間が変わりますので、その方それぞれの丁度よいタイミングを提案しております。慢性化してしまって皮膚がごわついているような状態の皮膚には地味な処置ですが、継続することがとても大切です。
みずいぼ(伝染性軟属腫)について
夏になると小さいおこさまをお持ちの方が悩まされるのが水いぼです。水いぼはポックスウイルスというウイルスが接触でうつるウイルス性のイボです。こどものうちは皮膚が薄くバリア機能が低いのと免疫を持っていないため感染しやすいのです。大人でうつる方もいます。
ひと昔前は積極的に摘除を行なっている時もありましたが、最近では小児科学会やこども家庭庁の指針においても摘除を積極的に推奨していないことと、プールの水で感染することはありません。接触で移るため、耐水絆創膏などで覆うことでプールに入ることができます。
物理的に摘除のみを行なっても体に抗体ができていなければすぐに再発します。
やむを得ず摘除を希望される場合は、こどもの場合10コを超えると表面麻酔を使っていても我慢ができないことが多いとご説明しています。当院では麻酔テープを貼付後、トラコーマ摂子で摘除しています。何かを塗ったり、液体窒素を使う方法もありますが、摘除が確実でないのと、かぶれをおこしたり、炎症後の色素沈着が強く残ったり、特に液体窒素は一箇所について数秒の時間痛みにたえなければいけないのでご本人にとってもつらいと思われるため当院では施行しておりません。
ウイルスが広がらないようにする予防は大切です。皮膚が乾燥した状態、いわゆるドライスキンがあるとウイルスが皮膚に入り込みやすく、広がるときは急に広がることもあります。特にプールなどの塩素にふれたときは皮膚の皮脂がおちてしまうので、肌の弱いこどもはプール後の保湿も大切です。
また、自費の化粧品の範囲にはなりますがMBFクリーム(2,000円)もご用意があります。
摘除をご希望の場合は予約制となりますので一度受診をお願い致します。
「できもの」の手術
皮膚の「できもの」については良性のものから悪性を疑うものなどいろいろあります。いわゆるよくあるホクロなどは正式名称を色素性母斑といって良性腫瘍なので保険適応の手術が摘除の基本となります。ホクロだけではありませんので術前の診断と、切除後の病理検査というのが大切です。万が一悪性であったり、追加の検査が必要なもの、そもそも腫瘍が大きすぎて大きな病院での手術が必要なものは大学病院形成外科へご紹介し、治療を行います。
当院では形成外科専門医が手術をします。一般に傷を何針縫ったという表現をされますが、形成外科の場合とても細い糸で細かく塗っていくことになりますので数字はおおきくなるかもしれません。
土曜日以外で院長診察の日は手術可能な日程となっております。空いている日程をご相談ください。
切除を希望される場合はまず受診をしてください。術前の診断から適切な手術の方法を検討させていただきます。
~流れ~
①最初の受診:術前の診断、術前の採血(手術や術後の処方の判断に必要な検査です。)、手術日の予約、手術内容についての同意書のご用意を致します。検査に異常があり手術困難な場合はご連絡致します。
②手術日:ご予約の日時にお越しください。手術時間は準備を含めて30分前後となります。
③手術翌日:初回の傷の消毒と出血の確認の診察を行います。傷の状態に問題がなければ翌日からは自宅で傷の処置をすることになります。処置の方法、必要な材料(院内購入可)はご指導致します。
④抜糸:およそ1週間後に抜糸となります。抜糸後はテーピングを行ったほうが傷がきれいに仕上がります。
⑤抜糸から1週間程度:切除したもの病理検査が届きますので、結果説明のため受診をお願い致します。
手術の内容にもよりますがおおよそ5回の受診が必要になります。
費用は自己負担比率や術式、処方内容により変動がありますが、3割負担の方でおよそ①~⑤で15000円前後となります。
お仕事やお休みの日程の調整などと合わせて予定をご検討下さい。
夏でも大事な保湿
だんだんと暑くなってきました。汗で皮膚炎が悪化している方も増えてきました。空気がじめじめしているので皮膚に保湿剤なんてぬったらさらにべたべたするのではと思われるかもしれませんが、実は大切なのは保湿です。エアコンの中での生活や、外で日焼けをすると意外と皮膚は乾燥してしまいます。特に紫外線ダメージの後の皮膚は乾燥が強くなります。
夏は汗で表面がべたべたしているようにみえますが、皮膚の細胞間の保湿ができていない(皮膚の水分量がへってしまう)と汗や油が皮膚にでてきたときにそれらが刺激になって皮膚炎をおこしやすくなってしまいます。
私たちが勧めているのは毎日の入浴後にする保湿(スキンケア)です。毎日顔に保湿(スキンケア)をするのは多くの人にとって当たり前になっていますが、体には何もしないという方が実は多いのです。体の皮膚の乾燥は皮膚のバリア機能低下の原因になります。冬は空気が乾燥しているため保湿力の高いクリーム基材のものを使いますが、夏は油分を抑えた透明なローションや乳液タイプのものをお勧めしています。
毎日保湿=スキンケアをすることで皮膚のバリア機能を維持して、汗や油に負けない皮膚にしていくことが大切です。特にアトピー性皮膚炎などの皮膚が乾燥しやすい体質の方はとても大切です。最近の手荒い、消毒などで手指の皮膚の乾燥も起こりやすい環境ですのでこまめな保湿はとても大切です。皮膚の状態にあわせて色々な保湿のバリエーションがありますのでご相談ください。
ケガ(傷)をしたら
突然の切り傷、擦り傷などのけがをしたときは血が流れていたり泣いていたり痛かったりしてどきどきしますよね。まずは落ち着いて、意識があるか自分で歩けるのかなど確認をしてください。もしそれらができないときは迷わず救急車を呼んでください。
特に全身状態に問題がなく、傷だけという場合は診療時間であれば当院へご連絡下さい。当院の形成外科医不在時や、皮膚科医のみで対応できないこともございますのでまずは電話でご連絡ください。また、傷は2日以上過ぎると縫い合わせることがむずかしくなるため、なるべく早くの処置をおすすめします。また、感染をおこしている傷も縫うことができません。縫合がむずかしい場合は別の方法を選択することがあります。
傷が汚れている場合は流水で洗い流せる範囲で洗い流してください。受傷後の感染を防ぐために大切です。傷が汚れていない場合は、汚れていない布やガーゼで圧迫して止血をしてください。抑えた状態で受診していただいて大丈夫です。受傷した場所や傷の状態によっては抗生物質を内服したり、破傷風のワクチンを使用したりすることがあります。
擦過傷などで市販の創傷被覆材などを使用される場合は、傷に雑菌が増えていないことが前提ですので、浸出液の量が多かったり、膿がでていたり、赤く腫れている状態での使用はおすすめしておりません。判断が難しい場合は受診をおすすめします。
傷が深い場合は局所麻酔をして、縫合が必要となります。当院ではなるべく傷がきれいに治るように形成外科医が縫合をおこなっております。
術後は次の診察日に受診をしていただき、状態がよければ抜糸までご自宅で処置を行っていただきます。傷をきれいに洗って、抗生物質の入った軟膏を塗ってガーゼをするなどの簡単な処置です。抜糸まではおおよそ1週間程度となります。
抜糸後は傷をなるべくきれいな状態で定着させるためにテープ固定やケロイド防止のための内服薬、外用剤などを使用します。
目立つような傷であったり、過去に受傷した傷跡が気になる場合などは修正のための手術などもありますのでご相談下さい。
全身の発疹(中毒疹)
全身にでる発疹といってもアトピー性皮膚炎の悪化や、蕁麻疹などのアレルギーや腫瘍関連の紅皮症といわれるものなどがありますが、季節の変わり目に多いと感じるのが全身に発疹ができる中毒疹といわれるものです。(アトピー性皮膚炎や蕁麻疹については別に書いていますのでご一読ください。)
中毒疹は主に薬が原因でできる薬疹といわれるものや感染症(いわゆる風邪といわれる数々のウイルス)が原因となるウイルス性発疹症と言われるものです。体の中に入ってきた異物に対して過剰な免疫反応が起こり皮膚に症状がでるものの総称です。薬疹の場合は原因と考えられる薬の内服を中止することが重要ですが、感染症(風邪)が原因の場合は体調を整えることがとても大切です。感染症の場合は風邪症状が治ったあとに免疫反応で皮膚炎が出てくるものもありますので注意が必要です。
軽症では抗アレルギー剤の内服(花粉症などで使います)やステロイドの外用剤と体調を整えることで改善します。中等症の場合は外来でステロイド内服などの治療をします。粘膜症状(目や口、陰部に痛みかゆみが強い)や全身症状、発熱などの重症の場合は総合病院への入院が必要な場合があります。当院では東京医科大学病院等へご紹介することが多いです。
薬剤が原因のものは内服中止などの経過をみて推定することができますが、感染症の場合は原因となるウイルスの種類が多岐にわたるため、よほどの典型的な皮膚炎をおこすものでなければ原因を特定することはできません。一般的に有名なもので水痘、麻疹、風疹、手足口病、突発性発疹などがありますが、全体からみると極一部の感染症です。
季節の変わり目は気を付けていても体調を崩しやすく、免疫が下がると風邪もひきやすくなります。体調管理はマスク、手洗いだけでなく、睡眠時間やバランスの良い食事をとることも大切です。
デュピクセント導入について
デュピクセントはアトピー性皮膚炎の新しい、ステロイドではない注射の薬です。痒みでつらい方、ステロイド外用剤の使用が頻回の方、慢性炎症による皮膚の赤黒い質感にお困りの方などに適応があります。最近では注射の薬よりは効果が緩徐ですが外用剤のコレクチムも発売されてアトピー性皮膚炎の治療の内容が格段に良くなりました。
デュピクセントの治療開始にあたっては、通院治療と在宅自己注射の2通りの方法があります。通院の場合は注射のために2週間に1回の通院が必要となります。受付をしていただいてから薬を常温において45分経過しないと注射ができないため、待ち時間などを気にされる方は在宅自己注射をおすすめしますが、自分で注射をする、準備する面倒などに抵抗がある方は通院をされています。
薬剤が高額のため国が定める高額療養費制度の利用をされたり(年収により負担額が変わります。)、ご加入の医療保険によって独自の付加給付制度が用意されている団体もあります。自己負担上限額が低く設定されていることが多いため、これによって導入を決断される方も多いです。大学生の場合は学校が独自に医療費負担を補助する制度を運営している場合もあります。ご希望の方から直接加入されている団体に直接お問い合わせください。他にもこどもへの医療費助成やひとり親家庭への医療費助成のある自治体などもあります。(病院から団体に問い合わせすることはできません。)
在宅自己注射導入をご希望の方は、初診・再診にかかわらず、まずは副院長の診察日にお越しください。皮膚のスコア(EASI、POEMという指標があります)を測定し、経過を記録するための撮影(背中・閉眼全顔)をします。ご自分で皮膚の画像をみていくと改善されていく過程を実感できます。また、注射剤の効果、副作用などについてご説明いたします。元々の皮膚炎症状が強い方の場合、副反応がでやすいことがあります。その対策のための処方などもあります。
通院注射を希望の方は初回注射の日程を予約致します。(予約注文制のため注射の納入に数日かかります。)
在宅自己注射をご希望の方は自己注射のための指導を看護師より2回受けていただく必要があります。この2日間は日時を決めての予約制となります。導入後の経過通院は大まかな日程でかまいません。指導1回目は動画をみていただいたり、薬の取り扱いについての説明や実際に自分でやってみる実技などの指導がありますので2時間ほど時間を考えておいてください。2週間後の指導2回目は実技の確認になる方がほとんどですので、1時間程度となります。しっかりと自分でできるようになるまで指導致しますのでわからないことがありましたらご遠慮なく仰ってください。
夜寝れるようになった、皮膚があれて血がでたりひび割れがなくなった、というPOEMのスコアが改善される方がほとんどです。導入後は保湿のみ、たまに湿疹ができたとき少し外用剤を塗るくらいというのが私たちの目標です。お悩みの方は是非ご相談下さい。
肌のかさかさ・かゆみ
乾燥を放置しているとかゆみがでますし、そこで皮膚をひっかいてしまうと細かい傷ができて湿疹ができたり、感染症をおこしたりなど様々な弊害ででてきます。
保湿でオイル、ワセリンを塗っているのに、というお声をよくききますが、乾燥の原因は皮脂、天然保湿因子、角質細胞間脂質の量が減って水分を保持できなくなることが原因です。水分が蒸発しているところにオイルやワセリンをぬっても効果が十分にでません。
水分をしっかり保水することが大切です。保湿剤といってもいろいろな種類があります。油分の多いものから水分の多いもの、使いやすい形状や塗りごごちなど様々です。保険診療の対象となります。
大切なのは毎日継続することですので、自分の生活スタイルにあった、毎回が負担になって面倒になってやめてしまうということがないようなものを選ぶことが重要です。何が自分にあっているかなど、ご相談ください。
(今回は首から下の四肢、体幹の保湿についての説明です。顔、首については少し変わります。体と同じ保湿をして顔に湿疹をつくってしまうこともありますのでご注意ください。)
デュピクセントにぺン型が登場しました
デュピクセントはアトピー性皮膚炎の治療薬として初めての「抗体医薬」です。「抗体医薬」は生体内にある免疫グロブリンと同様の構造をしたたんぱく質です。デュピクセントは、IL‐4とIL‐13の受容体に共通する分子に選択的に結合することで、IL- 4とIL-13の受容体への結合をブロックする薬です。
昨年末まではシリンジ型(注射器型)のみでしたが、年末からペン型が新しく発売されました。
シリンジ型はいわゆる注射を自分でするため、針をみるのがこわい、痛そうなど心理的なハードルが高いものでしたが、ペン型はキャップをとって皮膚に押し当てると、自動的に中で針が出て、自動的に薬剤が注入されるというとても簡単なものになりました。全過程で針をみることなく終了するため簡単にできるため、こちらに変更される方もいらっしゃいます。
アトピー性皮膚炎は皮膚の2型の炎症の免疫反応が強くでてしまう状態です。それによって少しの刺激でも強いかゆみがおこったり、とても赤くなってしまったりと過剰な皮膚の炎症を起こしてしまいます。様々な免疫物質が関与しているのですが、デュピクセントはそのうちの大きな要因となっているIL-4と13というところをブロックして炎症反応を起こさないようにする薬です。
副作用は多いものは結膜炎(目がかゆくなるなど)や、炎症の度合いが強い方などは投与の初期のころに筋肉痛や関節痛、発熱などの風邪に似たような症状がでることがあります。出ることが予想される方には事前に対処するための薬を処方するなどして対応しています。ヘルペスを誘発することもありますが、アトピー性皮膚炎をお持ちの方はもともとヘルぺスウイルスに弱い方もいらっしゃるので対処のための薬を処方致します。その他副作用については受診時ご説明させていただいております。
保険適応でも高額になってしまう薬ですが、その分の効果は十分に感じていただけているようです。まずは加入されている健康保険組合へ、付加給付制度や高額療養費制度など使える補助を直接ご自身でお問い合わせ下さい。
花粉症
花粉に敏感な方は症状がでる時期になってきました。植物の花粉に感作されることでおきる過剰な免疫反応です。
今の時期は主にスギ花粉症です。2~4月ごろにくしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、倦怠感、頭痛、のどの違和感、皮膚のかゆみなどの症状がでてきます。当院では症状のレベルにあわせて内服薬を組み合わせたり、目薬や点鼻薬などの治療をおこなっております。コンタクトレンズを装着しても可能な点眼薬もございます。
花粉が皮膚についたことによる刺激でおこる花粉皮膚炎は主に顔や首にかゆみをおこします。治療には外用剤や、皮膚保護剤が必要です。内服薬は主に抗アレルギー剤やロイコトリエン拮抗薬です。1日1回内服の薬や1日2回のものがあります。また、症状の強さや眠気の出現度合い、生活リズムなどによって種類を調整をしておりますのでご相談ください。内服治療が安定的であればオンライン診療も対応しておりますので担当医へご相談ください。
当院では舌下免疫療法はおこなっておりません。適宜、他院へご紹介をしております。
花粉症は感作がすすむと交差反応と言って果物や野菜をたべたときにアレルギーを起こす状態になってしまうことがあり注意がひつようです。今の時期に多いスギ花粉はトマトにも反応してしまうことがあります。他にも有名なものはシラカバ、ハンノキ花粉症です。リンゴやモモなど果物でOAS(口腔アレルギー症候群)を起こすことがあります。食べたときに口の中に違和感がでたり腫れたりしてしまうことがあります。血液検査でアレルギーをしらべることもできますので、気になる症状がある場合はご相談ください。
大豆成分エクオール
古くから大豆製品は日本人の食生活になじんだ健康食材です。大豆は女性ホルモンのエストロゲンとよく似たはたらきの成分を含むため、元気と若々しさを保つのに役立つと言われています。
エクオールは大豆の中のイソフラボンが腸内細菌の酵素によって変換されて、エストロゲン様の働きをします。ところがこのエクオールに変換する力がアジア人では50%程度の人にしかありません。欧米では20~30%程度です。イソフラボンのサプリメントをとっていてもあまり効果を実感できないという方はあてはまるかもしれません。
このイソフラボンをエクオールに変換する力があるかどうかを尿検査キットで簡単に調べることができます。只今3箱ご購入の方には1箱無料でついております。
エクオールはエストロゲン様作用(エストロゲンによく似たはたらき)、抗酸化作用、抗エストロゲン作用(本来のエストロゲンのはたらきを抑える)、抗アンドロゲン作用(男性ホルモンのアンドロゲンのはたらきを抑える)があります。更年期の症状をやわらげ、骨、皮膚、血管など全身を守る働きをします。
hエストロゲン様作用は更年期障害の症状をやわらげます。1日1回以上ホットフラッシュがある女性が3か月以上エクオールを摂取したところ、症状の回数が58.7%減少しました。目じりのシワなどの肌の弾力についてもエクオールを内服している群としていない群でしわの面積が抑えられたという結果がでております。また、骨密度の減少を抑えるなどのはたらきもあります。
年を重ねると手指のフシのボコボコ(腫れや痛み)がでてきます。関節の周囲にある滑膜の柔軟性が衰えて炎症を起こしやすくなるためです。炎症の起こしやすさは人によりますが、エストロゲンが血管を拡張し、滑膜の柔軟性を保っていることがわかっています。も、エクオール産生能を持つ人と、そうでない人で大きく差がでております。すでに変形している関節を治す薬ではありませんが、今後の変形を予防するはたらきがあります。
また、女性の薄毛の原因にエストロゲンが減る事によって髪が細くなったり、コシやハリがなくなってきます。男性の薄毛と女性の薄毛は明らかに機序が違うため、いわゆるAGAの治療を女性がうけてもあまり効果がありません。薄毛の女性とそうでない女性のエクオール産生能にも大きな差があることがわかっています。すでに薄くなってしまったところの毛をはやすことはできませんが、毛の量を維持してハリやコシを保つ効果があります。
乳がん経験者のヘルスケアにも使われています。エクオールを摂取することで、過剰なエストロゲンよりも先にエクオールが受容体にはまりこむことで、過剰なエストロゲンの作用を弱めるはたらきがあります。エクオールを摂取することで乳がんになりやすくなるということはありません。結果的にエクオール摂取をしている人のほうが健康が維持できているという結果もでています。
※治療ではなくあくまでもサプリメント(食品)です。
皮膚・髪に大切な亜鉛
亜鉛は鉄分とならぶ体に大切な栄養素です。亜鉛欠乏の患者さんは世界で焼く20億人いるとも言われています。当院に受診される方の中でも比較的に若いのに最近生え際が薄くなってきた、抜け毛が多くなってきたと言われる方がいらっしゃいます。採血をして亜鉛の数値をはかると亜鉛が基準値より低いことがわかります。食事が外食ばかりだったり、好きなものだけをたべていたり、社会人になって一人暮らしをはじめたばかりで食事の管理にまだ慣れていない方に多いです。食生活を見直すことがとても大事で、必要な量がとれるようになると薄毛は回復してきます。
他にも亜鉛欠乏は下痢や味覚障害をおこしたり、皮膚が刺激に弱くなる、皮膚免疫能の低下、傷の治りが遅くなるなどの影響があります。口のまわりや手指、足先、おしりなど繰り返し刺激をうける部分にできる腸性肢端皮膚炎もこのような一次刺激が原因と言われています。口の周りに皮膚炎をおこしやすく、できた皮膚炎が治りにくいにでさらに悪化するという悪循環がおこります。ですが、口回りにできる皮膚炎と言ってもいろいろなものがあり、脂漏性皮膚炎などの症状にもよ現れます。よくわからないときは医師にご相談ください。一度受診されることをお勧めします。また、亜鉛がしっかりとれているかな?と一度食生活を見直すことも大事です。
サプリメントで亜鉛を摂取することもできますが、基本的にはバランスの良い食事をとることが大事です。亜鉛を多く含む食品は豚肉、レバー、卵、チーズ、カキ、アワビ、タラバガニ、高野豆腐、納豆、えんどう豆、切り干し大根、アーモンド、落花生などです。同時に、アルコールの多飲や穀物や豆類に含まれるフィチン酸をはじめ乳製品に含まれるカルシウム、コーヒーのタンニンなどは亜鉛の吸収を阻害します。食物繊維や青菜に含まれるシュウ酸も亜鉛吸収を阻害するので、肉の摂取量が少なく、野菜ばかりなど、偏ったダイエットなどをされている方は要注意です。しかし、何事もやりすぎはお勧めしません。バランスのよい食生活(分量、栄養素の配分など)が大事です。
※女性の薄毛の原因は亜鉛欠乏だけではありません。脱毛専門クリニックなどで一般的な男性がするAGAの治療内容の適応も慎重に考える必要があります。
皮膚科の外用剤指導って?
アトピー性皮膚炎や脂漏性皮膚炎、酒さ、にきび(尋常性ざ瘡)で「皮膚科に行って治るはずの薬をもらったけど治らない」という時は使っていたお薬や普段使っている化粧品(基礎化粧品から)を持っていらしてみてください。皮膚科治療の大切なことは、内服薬と違って使う順番、塗る量、範囲、どんな症状の時にどんな薬を塗ればよいかということを丁寧にお話しすることがとても大切です。1番目に塗るか、2番目に塗るかというだけで効果が全然変わってきます。効かないとおっしゃる場合、よくあるのが塗る順番の違いです。化粧水を先につかっているのか薬を先に使っているのかというだけで効果は全く違ってきます。特に経過の長いアトピー性皮膚炎、すぐには治らない脂漏性皮膚炎、日常生活にとても影響をうけてしまうにきびの治療など、それぞれどんな時にどういうものをどれくらい使ったらよいか、どんな化粧品をどんな成分のものに変えたら良いかということをお話ししております。はじめは変えることが多く、混乱してしまわれる方もいらっしゃいますが、わからなければその都度何をどうしたらよいかということをお話ししております。迷ったらまずはご相談ください。徐々に自分のペースと通院間隔と、外用剤の使い方がつかめてくると症状が安定してくる方がほとんどです。体調が悪化したり疲れがひどかったりすると皮膚炎が急に悪化することもありますが、対応方法がわかっているとひどく悪化することなくトラブルシューテイングを自分ですることができるようになります。
外用剤の種類や強さも大切です。日常の生活のペースは人それぞれなので、何をどれくらいのペースで使っているかということも薬の種類を決定する大事な要素です。ステロイドと一言でいっても使い方や種類は多種多様です。とても弱いとされるステロイドでも使う頻度やタイミングによっては副作用が出やすい使い方になってしまっていることがあります。皮膚炎の症状の内容や外用のタイミングなどをによってはステロイドではない薬の方がよい方もいらっしゃいますし、ステロイドをうまく使った方がよい方もいらっしゃいます。使ってみたけれど合わない、よくならないという場合もあります。そうしたことを積み重ねてその方一人一人にあった治療法を一緒に見つけていくことがとても大切です。
保険診療のニキビ治療は効かない?
世の中のニキビの治療には化粧品から、美容診療まで様々なものであふれています。効果のあるものから、根拠に乏しいものまであります。その中で保険診療で認められている外用薬は厳しい治験をパスしてきたしっかりとした効果のある薬です。
今まで色々なクリニックで薬を出されたけれどどれもあまり効果がなかったとおっしゃって受診されるかたも多いのですが、実際にお話を聞いてみると実は塗り方が違っていた、塗る範囲が違っていた、塗るタイミングや順番が違っていたということがあります。
ニキビの外用薬はいつ塗るか、どの範囲に塗るか、塗る順番、化粧品と薬どっちをどの順番に塗るのか、というのがとても重要ですし、それを変えただけで薬の効きが変わって改善していきます。
化粧品も基礎化粧品、メイク化粧品色々なものがあり、何がニキビに悪いかということもアドバイスさせていただきます。
当院のニキビ治療では洗顔からその後何をどの順番にどの範囲に塗るかということをアドバイスさせていただきます。初めは混乱してうまくできないこともあります。症状の改善に合わせて色々と範囲や順番も変わっていきます。ただ同じ薬を延々と塗ってれば良くなるというものではありませんので、最初の受診からまずは2週間後、薬の調整をしてまた2週間後、その後は状況や生活に合わせて1ヶ月ごとの受診、自分でトラブルシューティングがうまくできるようになったら2.3ヶ月に1度の受診と、段々とペースを掴めるようになっていきます。
炎症の状況によっては抗生物質の内服をすることもありますが、これも様々な薬があり、炎症の度合いによって使う薬も変わりますし、できるタイミングや、どのように悪化の波が来るのかというのは人それぞれですので、それに合わせて処方と内服のタイミングをアドバイスさせていただきます。
もし今までのニキビ治療がうまく行かなかったという方は、今までに使った薬やどのように使っていたか、どのような化粧品をどのように普段使っているかということを教えていただけるとうまく治療につながります。安易に美容治療に進むこともおすすめはしておりません。肌の状態に合わせて保険診療が適切なのか、美容診療が適切なのについてもアドバイスさせていただきます。
尋常性乾癬の治療薬オテズラの導入について
尋常性乾癬は免疫のバランス異常によって起こる全身の炎症性疾患です。発症は1000に4.5人の割合で中年の男性にやや多いと言われていますが、全年齢層、女性にもみられる疾患です。人にうつるものではありませんが、人からみられる所に症状があると精神的な苦痛を感じる方も多いです。一見症状がない場所でも刺激を加えることで新しく症状が出たり、広がる性質があります。よくなったり悪くなったりを繰り返すので、長期的なケアが大切です。
乾癬の原因ははっきりとわかっていませんが、なりやすい遺伝的な要素と環境的な要素が複雑に影響して発症します。皮膚炎は特に摩擦を受けやすい肘や膝、腰まわり、頭皮や爪にも出やすいです。重症な場合は関節にも影響して変形や痛みを伴います。
治療法は保険診療の中で大きく分けて外用剤、内服、注射剤、光線療法とあります。今回導入したオテズラは中等症の方に適応があります。中等症はざっくり言うと関節症状が比較的軽く、皮膚炎が広範囲または外用剤に反応が悪いなどです。オテズラはPDE4阻害剤と言われるものです。PDE4は体の中の細胞にある酵素で炎症を引き起こす物質の産生に関わっています。乾癬の方の皮膚や免疫細胞で通常よりPDE4が多くあるため、免疫バランスの異常が起こります。オテズラはその働きを抑えることで乱れた免疫バランスを整え、炎症を抑えて乾癬の症状を改善します。
オテズラ内服後の改善までは個人差があります。飲み初めから24週くらいを目安にゆっくりと症状が改善してくる方が多いです。薬は飲み初めの頃に吐き気や下痢、頭痛がみられることがあります。2週間目から出現して4週目以内におさまることが多いのです。稀ですが感染症や過敏症、重度の下痢が現れることもあります。
安定してくると外用剤を毎日塗るストレスから解放されて皮膚が綺麗な状態が保てますので日々の生活が楽になると思います。
より詳しい内容については皮膚科専門医の診療時間帯に受診をお願い致します。